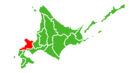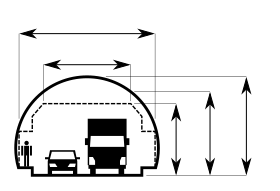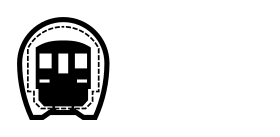畚部岬
(新畚部から転送)
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
畚部岬は小樽市と余市町の境界にある岬。岬の付け根には道路トンネルがあり、300mほど内陸には鉄道トンネルがある。
道路1代目
|
ふごっぺ
畚部
北海道 トンネルwiki ID:530415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小樽と余市の間の道路は多少の起伏はあるが徒歩での通行に大きな障害となる険路ではなかった。しかし道の状態はあまりよくなかったため1878(明治11)年12月改修に着手、1882(明治15)年に完成した。工事は沿線住民らの寄付奉仕により、多くは本業の漁業の合間を利用して行われた。この工事により畚部岬を貫くトンネルが初めて穿たれた。
道路2代目
|
ふごっぺ
畚部
北海道 トンネルwiki ID:704500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路3代目
|
しんふごっぺ
新畚部
北海道 トンネルwiki ID:938875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先代のトンネルは幅員が狭く交通上のボトルネックとなっていたため、これの解消を目指す「栄町中央帯整備事業」が2008(平成20)年事業化した。2015(平成27)年に着工し海側の隣に新トンネルを設け、先代と本トンネルの2本で上下線(各1車線)を分けるセパレート交通を採用した。工事延長は500m。2018(平成30)年12月7日6:00に小樽へ向かう車線を一時停止し、5分後にセパレート方式の供用を開始した。
鉄道
|
らんしま
蘭島
北海道 トンネルwiki ID:656851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道鉄道線のトンネルとして着工。6月5日小樽方坑口で導坑が着工、7月9日反対の函館方でも着工、7月28日に貫通した。